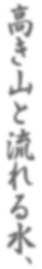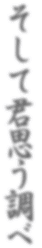最終話
橘の花香る五月の午後。
常緑樹の緑生い茂る初夏のとある寺を、訪れる者たちがいた。
年は五つか六つぐらいだろうか。よく日に灼けた肌をした黒髪の少年は、父親と思しき背の高い男と手をつなぎながら、寺の裏手にある墓地へ続く参道を歩いている。
途中の道でこの寺の年老いた住職とすれ違う。父親の男は丁寧にお辞儀をして、一言二言世間話を交わすと、もう一度会釈をしながら少年の手を引いて参道を歩き出した。
墓地に入ると、少年は備えつきの手桶に水を入れて手に持った。
父親に「重くないか?」と少し心配げに尋ねられたが、少年は元気な声で「平気だよ」と答えて首を振った。
そのまま水を入れた重い手桶を持って、えっちらおっちらした足取りで進んでいくと、やがて少年の家の墓へと辿り着いた。
男が手に持っていた花束を墓前に置いて、マッチで火を灯した線香を供える。
少年はちょっと煙いのを我慢しながら、手桶の水を柄杓で墓石にかけた。けれど彼の手の長さでは墓石の上の方にかけられないので、父親に抱き上げてもらって水をぴしゃりと上からかけた。
二人並んでしゃがみこみ、手を合わせながら墓の前で目を瞑る。
目を開けてみても、隣の父親はまだ目を瞑って何かお祈りしているようだった。
少年がちょっと退屈そうに辺りをきょろきょろしていると、ようやく父親が瞼を開けて、優しい瞳でこちらを見た。
「幸綱。ちゃんとお母さんにご報告したのか?」
父親に聞かれて、少年はコクコクと顔を頷かせた。
「ちゃんとしたよ。お家のお手伝いもしてるし、お父さんやお祖父ちゃんたちの言うことも聞いてるし、お友達ともけんかしてないよって。ちゃんとお母さんにご報告した」
少年が一生懸命そう言うので、父親は優しく微笑んで、「そうか、えらいな」と褒めながら大きな手で頭をぽんぽん叩いた。
「……ねぇ、このあと健吾にいちゃんたちといっしょに遊ぶ約束してるんだ。お母さんのお墓参り済ませたから、もう行っていい?」
健吾というのは、ここの寺の隣に住む小学生の少年のことだった。この辺りに住む少年や少女たちを引き連れて、近所を遊びまわっているのをよく見かける。……いわゆるガキ大将というやつだ。
「……いいよ。あんまり遠くに行くんじゃないぞ」
「うん。あのねぇ今日は健吾にいちゃんたちの秘密のきちに連れてってもらえるんだよ」
少年は満面の笑みを浮かべながら、嬉しそうにそう報告した。
「そうか。楽しそうだな。健吾君たちとはぐれないように気をつけなさい。それとあまり遅くならないように」
「うん、大丈夫」と少年は無邪気に微笑むと、くるりと踵を返して駆け足で去っていく。
その後ろ姿を見送っていると、角を曲がる瞬間に、出会いがしらに誰か人とぶつかったらしい。
少年が後ろによろける姿を見て、男はすっくと立ち上がった。
「幸綱」
慌てて駆け寄ろうかと思ったが、その瞬間ぶつかった相手が手を伸ばして、よろける少年の体を支えた。
「大丈夫?」
そう聞いたのは、紺色の着物に身を包んだ青年だった。
「……うん、大丈夫」
コクコク頷く少年に向かい、青年は優しい笑顔を浮かべた。
きつめの眼をしていたが、笑うととても親しみやすい印象になった。
そこに父親が歩み寄ってきたので、腰を屈めていた青年は顔を上げた。
「すみまさん、息子がご迷惑をおかけし………………」
少年の肩を抱きながら謝罪の言葉を述べようとして、そのまま男は固まってしまう。
茫然と、目の前の青年を凝視している。
そして青年の方も、現れた男の姿を見て目を見開いていた
紺色の着物の青年の、顔を凝視しながらぴくりとも動かなくなってしまった父親の様子に、少年は訝しそうに眉を顰めた。
「どうしたの?」
男がはっとして、少年の顔を見た。
「……いや、なんでもないよ」
「もう行ってもいい?」
「ああ、もちろん……」
少年は父親の了解を得ると、ぶつかった青年にぺこりと丁寧にお辞儀をして、そのまま駆け去って行った。
男はもう一度青年に視線を移し、信じられないといった面持ちでそのよく整った顔を凝視していた。
そしてかすれた声音でその名を呼ぶ。
「高耶さん……」
高耶と呼ばれた青年は、惑うように両眼を揺らしている。
最後に彼に会ってから、もう何年目になるのだろう。
紺の着物を着流しにした彼は、以前とあまり変わらぬ姿でそこにいた。
相変わらず痩せてしなやかな身体に、日に焼けた肌。短い黒髪。
凛々しい目元も変わらない。それにもとより大人びた風貌をしていたが、年相応に落ち着いて、少し男らしさが増したようにも思う。
彼は、高耶は、後ずさりかけていた足に力を込めて、正面に佇む男の顔を見た。
「……、直江か」
感情を押し込めたような小さな呟きに、男は大きく顔を頷かせる。
「ええ、お久しぶりです……」
高耶は苦しげな表情を隠さぬままに、長く会わなかったこの男との再会を果たした。
直江の方も、あまり変わっていなかった。
どころか、頭の中に残っている最後に会ったあの時の姿とほとんど変わった様子がないので、高耶は内心動揺していた。
「息子さん、か?」
しばしの重い沈黙を破ったのは、高耶のそんな問いかけだった。
「……ええ、幸綱というんです」
その肯定が、姿形はあまり変わっていなくても、確かな時の流れがそこにあることを感じさせた。
ここにいる彼は、もはや高耶の知る直江ではないのだった。
「……そうか、利発そうで、かわいい子だな」
翳りを帯びた言葉に、何と返して良いのか分からなくて、直江は曖昧に微笑んだ。
素直に礼を言えば良かったのだろうか。
「ここへは、どうして?」
直江の問いに、高耶は少しの間黙り込んだ。
惑うように目線を揺らし、やがて言い辛そうに答える。
「……舟子さんが、亡くなったと聞いて」
直江は得心したように頷いて、無表情に「そうですか」と呟いた。
二人の間に、気まずい空気が流れていた。
風が深緑のこずえをさわさわと揺らす。
直江はそのまま無言で踵を返し、元いた方向へと戻っていった。
高耶も何も言わずに、直江の後をついていく。
ややもせずに、二人は一つの墓石の前に辿り着いた。
御影石の墓石には亀甲花菱の家紋の下に、「直江家之墓」と掘り込まれている。
先ほど供えたばかりの線香が、ゆるく煙を上げていた。
高耶はいままで手にしていた小さな花束を墓前に置いて、片膝ついて合掌した。
直江はしばらく彼の様子を眺めていたが、やがて静かな口調で語った。
「妻が死んで、もう四ヶ月近くになります」
黙祷していた高耶は、閉ざしていた瞼を開けて、「……そうか」と低い声で呟いた。
「あっけないものですね、人の命というものは……。さっきまで普通に生きていたと思ったのに、突然、いなくなってしまうんですから……」
どこか人事のように直江は語った。妻を亡くした夫の言葉とは思えぬほど、口調はひどく淡々としていた。
「……病死、だったんだよな?」
問いに、直江はすぐさま首を振った。
「いいえ、自殺です」
高耶が息を飲んで振り返る。視界に映った直江は、依然として無表情なままだった。
「外聞が良くないので、病死ということにしてあります……大分前から精神の方を患って、通院を繰り返していたものですから」
高耶は顔を強張らせていた。
可憐でありながら、気丈な少女だった。そんな彼女が自殺だなんて、俄かには信じられない。
その青ざめた顔を見つめながら、直江は抑揚の少ない口調で言葉を続けていった。
「もとより、夫婦仲は決して良いとは言えませんでした。最初の頃は私も優しくしようと努めていたのですが、妻が……舟子さんが、嫌がるんですよ」
「……なぜ」
短い問いに、直江が苦い顔で呟く。
「心にも無い優しさなど、欲しくないと……」
偽りの優しさなど、掛けられた所で虚しいだけだと。
その答えに、高耶は沈痛そうに眉を顰めた。
彼は、彼女の苦悩の意味を知っていた。そしてその直接の原因が、自分にあるということも。
「……次第に会話をすることもなくなっていきました。表向きは仲の良い夫婦を装っていたけれど、関係はこれ以上無いくらい冷え切っていました。けれど、私には彼女を責める権利は無かった。彼女が妊娠したと聞いたときも……」
直江は一つ呼吸を置いて、自嘲するようにかすかに笑った。
「すぐに私の子ではないと分かったけれど、私は一言も責めはしませんでした」
高耶がそこで顔を上げた。目を瞠りながら、背後に立つ直江の気配を窺う。
「何も言わずに、私の子と認めたんです。……けれど、彼女にはかえってそれが堪えられなかったんでしょうね」
舟子は、本当は産むつもりなどなかったのかもしれない。
ただ直江の反応を試そうとしただけだったかもしれない。
しかし直江は、彼女を責めたてもせずに、舟子が妊娠した旨を両親へと報告したのだった。
直江から報告を聞いた義父母は、大変な喜びようだった。すぐさまこの吉報は親類へと伝わっていった。
あの時の自分を見つめる舟子の表情は、いまでも忘れられない。
先に裏切ったのは彼女のはずなのに、直江に手ひどい裏切りを受けたような顔をしていたのだ……。
「彼女の為に良かれと思ってしたことが、結果的に、彼女を精神的に追い詰めてしまったんです……」
そして舟子は、幼い息子を残して去って行った。
せめて娘であったなら、あそこまで追い詰められることもなかったかもしれない。けれど生まれた子は、親類一同が長らく待ち望んでいた、跡継ぎの男の子だったのだ。
不義の子である幸綱を、直江の子として、ましてや跡取りとして育てていくのは、彼女の精神では堪えられなかったのだった。
最後の方では、幸綱の顔を見ることすら厭うようになっていた。
……どうしてあんなことになってしまったのだろう。
直江は苦しげな表情で、亡き人の眠る、黒い墓石をじっと見つめた。
「……私は、幸綱が生まれて、嬉しかったんですよ」
まるで彼女に語りかけるように、直江は告白した。
冷えた関係だったが、彼女への関心が無いわけでは、決してなかった。
もはや夫婦として愛し合うことができないことは分かっていた。ならばせめて幸綱が生まれたことをきっかけに、子供を通して穏やかな家族関係を築くことができればいいと、本気でそう思っていたのだ。
けれど彼女は、それでは満足できなかったのだろうか。
高耶は少し考えるようにして、静かな声で言った。
「彼女はきっと……おまえのことが、好きだったんだな」
「……そう、かもしれません」
噛み締めるようにそう言って、直江は目を瞑った。
高耶は墓石に供えられた、細い煙をあげる線香を一筋に見つめていた。
唇を噛み締めて、紺色の単の裾を掌に握り込む。
「結局ぜんぶ、オレのせいだな……」
突然呟かれた言葉に、直江は閉じていた瞼を開けた。
墓前にしゃがむ高耶の横顔は、どこか苦しげに歪んでいた。
右手の拳を、爪が食い込むほどにぎゅっと握り締める。
静かな初夏の墓地の中で、高耶は眉間に皺を刻みながら、「でも……」と、搾り出すように告げた。
「おまえたちが……幸せになんかならなければいいって、どこかでそう願ってた……」
俯いた頬に、前髪がかかる。
直江は瞠目しながら、落ちかかる黒髪に隠された、彼の横顔を見つめていた。
歯を食いしばって、顔を俯かせる高耶の顔。
この顔を、こんなにも近くで見られることは、もう二度とないと思っていた。
直江は痛みを発する左胸のあたりを、右手で抑える。
そして懊悩するように首を左右に振りながら、彼は真摯な声で高耶に告げた。
「私は、それでもあなたと出逢えたことを、後悔したことなどありませんでしたよ」
高耶が少しだけ顔を上げた。
直江は一歩前へと歩み寄り、振り返らない青年の背中に向けて、告白した。
「私はいまでも、あなたのことを愛しています……」
びくりと揺れた肩越しに、高耶の表情が見える。
驚きに眼を見開く様は、二十歳を過ぎた青年を、少し幼く見せていた。
「あの日から、いままでの間、あなたのことだけをどんな時も想い続けていました」
ゆっくりと振り返る。男の瞳と視線が絡む。
かつてと変わらぬ鳶色の瞳は、これ以上ないくらいの愛しさに溢れていた。
「あなたを愛しています……」
魂を込めた囁きが、耳に届いた。
高耶は、声も無く瞠目していた。
直江の端整な造作をした目元の辺りを、ひたと見つめ続ける。
そして頭のどこか冷めた部分で、冷静にいまの状況を分析していた。
この男は、どうして、いまになってこんなことを言うのだろう。
その言葉を欲していたのは、いまじゃない。
あの頃の自分が、どんなに欲しても手に入れられなかった言葉を、どうしていまになってこの男は口にするのだろう。
もう、終わったことなのに。
何もかも過去のことなのに。
どうして今頃になって……。
「あなたはもう……私のことなど、忘れてしまいましたか」
答えのない高耶に、直江が問いかける。
真摯な眼で、こちらを真っ直ぐに見つめている。
逃れぬように、視線の鎖で高耶を絡め取る。
「もう一度、やり直すことはできませんか」
瞳を揺らした。
眼の奥の辺りが、途端にずきりと痛みを発して、高耶は声も無く俯いた。
痛みで目元に涙が滲む。それを堪えようとして、高耶は口元を右手で覆い隠しながら、顎が痛くなるぐらい奥歯を噛み締めた。
「…………無理だ、直江……」
歯の奥の辺りから、痛みに耐えるような声が漏れ出でた。
そのまま強く瞼を瞑る。まるで子供がそうするように、頭を左右に横に振った。
「オレには、彼女を傷つけた罪を、背負うことなんてとてもできないよ……」
舟子を追い詰めた原因の一端は、間違いなく過去の自分にあるのだ。
おそらく彼女を傷つけることになるだろうことを承知の上で、高耶はあの時笛を吹いた。
傷つくなら、傷ついても構いはしないとさえ思っていた。
それは自分を差し置いて直江と添い遂げる彼女に対する、報いの刃なのだとすら思ったのだ。
幸福になど、なってはならなかった……。
そんな自分の醜さを、高耶は誰よりも知っていた。
知っているからこそ、この上自分が直江と結ばれて幸福になる権利など、ありはしないのだと思っていた。
俯いたまま、何も言わずにいる高耶を見下ろしながら、直江は苦しげな声音で問うた。
「本当に、駄目なのですか……」
瞳の中に、哀しみに歪む光が閃く。
ゆるゆると首を降り続ける高耶の背中に向かって。
最後の確認のように。足掻きのように……直江は高耶に尋ねた。
「あなたは……私のことをもう、愛してはいませんか」
墓地に涼しい風が駆け巡る。
喧騒すらない午後の住宅街の中で、一瞬の沈黙の後、高耶は言葉も無く、こくりと顔を頷かせた。
直江はその光景を、黙ったまま見つめていた。
何も言わずに、高耶の俯く横顔を見つめていた。
中天にあった夏の太陽が、雲の合間に隠れて、少しずつ翳りを見せ始めていた。
遠くから子供達の楽しげに遊ぶ声が聞こえていた。
その中に、幸綱の笑い声も聞こえるような気がする。
もう、そろそろ戻らなくてはならない……。
先ほどからぴくりとも動こうとしない高耶の肩のあたりを見つめながら、直江は静かな声で言った。
「……最後に、一つだけお願いしてもいいですか」
直江は、下に置いていた革の鞄から、何か布の袋を取り出した。
その袋の口を開けると、中から出てきたのは細い篠笛だった。
焦げ茶色に塗られた、天地籐巻き十本調子。
「私がここを立ち去る間、私の姿が遠くに消えるまで、この笛を吹いていてくれませんか」
その笛を高耶の方にすっと差し出しながら呟く。
高耶は茫然と、その篠笛を見つめていた。
それは確か、高耶がかつて『伯牙』という銘をつけた、思い出の笛だった。
高耶が壊した『鐘子期』という笛と、対につけられた篠笛。
途端に、懐かしい心地に襲われた。
あの頃の思い出が、まざまざと甦ってくる。
ふたりが出逢って、間もないころの思い出が……。
篠笛を凝視したまま、受け取ろうとしない高耶に、直江はそっと語りかけた。
「私はもう、振り返りません。ここから何も言わずに立ち去ります。だから、最後の手向けにあなたの笛を聴かせてください」
そこで息を吸って、決意をこめた声音で、言った。
「これで、……今度こそお別れにしましょう」
高耶は瞳を閉じて、ぎゅっと拳を握りしめる。
そしてゆっくりと右手を差し伸べ、その篠笛を受け取った。
「……わかった」
ひどく苦い言葉を、そっと唇の上に乗せた。
高耶は立ち上がり、直江の隣に立つと、斜め上方向にある背の高い彼の整った顔を見つめた。
今度こそ、これが最後だった。
もう二度と彼に会うことは無いと、そういう決意を込めて、高耶はひたむきに直江を見つめている。
細められた鳶色の瞳には、あの時と何も変わらず、ただ高耶へのみ向けられた愛に溢れている。
その優しい瞳が、切なげに揺れた。
「……さようなら、高耶さん」
彼は哀しく微笑みながらそう告げると、ゆっくりとした動作で踵を返し、そしてそのまま去っていく。
名残を惜しむように、その背中を見送っている。
高耶は断ち切るように顔を俯かせて、そうして墓石の方に振り返ると、篠笛を構え、眼を瞑ってその歌口に唇を乗せた。
そしていま心にある思いを移し込むように、魂をこめて息を笛に吹き込む。
ピィィィィ────────。
涼やかな音が、その場に響き渡った。
もう随分長いこと、篠笛を吹くことはなかったのに、身体が記憶していたのだろう。澱みない動作で高耶は笛を吹き続ける。
ピピィィィ──────…………。
その美しい音を背中越しに聴きながら、直江はゆっくりと参道を歩き続ける。
次第に遠くなる背中。
高耶は直江の方を見ない。目を閉ざしながら、ただ想いをこめて篠笛を吹き続けていた。
徐々に足音が遠ざかっていく。
吹き続ける間、高耶の脳裏には直江との思い出がまるで走馬灯のように浮かび上がっていた。
初めて出逢った初夏の夜。
笛を聴かせてほしいのだと、懸命な声で頼み込んでいた。
家を訪ねて行ったときも、暖かく出迎えてくれた。
蛍の光る夜道を二人並んで歩いた。
秋には金木犀の香りの中、肩を並べて家路を歩んだ。
さまざまなかけがえのない思い出が、砂時計の砂がこぼれ落ちるように、心の中に甦る。
病院にも毎日見舞いに来て、高耶を励ましてくれた。
お祝いにと渡された素竹の篠笛は、一番の宝物だった。
桜の花の中、困ったようにこちらを見上げていた瞳。
そして式の日に、彼が最後に見せた哀しい笑顔を、高耶は一瞬も忘れたことがない。
いつも優しい瞳でこちらを見つめていた。
優しい声で、名を呼びかけた。
こんなに幸せな瞬間は、他にないと思った。
愛していないなんて、嘘だった。
いまでもこんなにも彼のことを想ってる。
何をするにも、どこに行くにも、彼のことを思い出さない日などなかった。
そして彼がここにはいないことを知って、堪えようのない痛みに涙をこぼした。
忘れられたなら、どんなに楽だったか。
愛していたのだ。
長い間ずっと。
もう二度とは返らない日々を胸に秘めて。
宝物のように、心の中に閉じ込めて。
それでも想いは蓋を押し開けてあふれだす。
言葉にならない想いが、笛を通して天に上がる。
行かないで欲しいのだと。
本当は、ずっと抱きしめて欲しかった。
罪だとか、過去だとか、そんなものはどうだっていい。
ただ抱きしめて欲しい。
そして自分だけのおまえでいて欲しい。
誰にも微笑みかけないで。
ずっとそばにいて。
優しい瞳で、自分だけを見つめていて欲しい。
そのかけがえのない愛を、奇跡のような想いを、
自分だけに与え続けていて欲しい……!
高耶はいつしか笛を吹くのをやめていた。
もう、直江は墓地から去って行っただろう。
次第にこらえようもない哀しみが全身に押し寄せて、口元から笛を離すと、両手で顔を覆い隠した。
指の間から、押し殺された嗚咽がかすかに漏れ出ずる。
止め処ない涙がぼろぼろと頬を伝って、足元に跳ねて落ちた。
しばらく高耶は、声を殺して泣き続けていた。
悲しみに心が破裂しそうだった。
その背中を不意に、優しく抱きしめる腕があった。
あたたかなぬくもりが、背中から広がっていく。
高耶はその腕の持ち主を知って、ゆっくりと顔を上げた。
覆い隠していた両手を顔から離して、嗚咽で切れ切れの声で呟く。
「……振り返らないんじゃ、なかったのかよ……っ」
涙に濡れる顔で呟いた高耶を、後ろから抱きしめたまま、直江は腕に力を込めてかすれた声で叫んだ。
「あなたのあんな笛の音を聞いて、立ち去れるはずがないでしょう……!」
直江は高耶の肩口に顔を乗せて、耳元に熱く囁くように言葉を続ける。
「一緒に、背負っていってください……彼女を不幸にした罪を。それは私だけが背負うには……とてもじゃないが重すぎる。あなたには私と共に背負う義務があるはずだ……」
抱きしめていた腕を離して、彼は高耶をこちらに振り向かせた。
高耶の両肩を掴み、真正面から、これ以上ないぐらい真摯な瞳を向けながら告げる。
「そして私の隣で、私のためだけに……あなたの笛を聴かせてください」
その奇跡のような篠笛を。
誰よりも近くで。
死ぬまで。一生……──────。
見上げる高耶の瞳から、涙が一筋こぼれ落ちた。
直江の笑顔がそこにある。
あんなにも焦がれてやまなかったその笑顔が、いまここに。
高耶はもう、何も考えられなくなって、ただ静かに瞳を閉じた。
これ以上の言葉は、もはや二人には必要ない。
直江はそっと顔を近寄せて、惹かれあうように唇を重ねる。
そのまま背に腕を回して、きつく抱きしめた。
高耶の手が、そろそろと直江の背を辿る。
二度目に交わした口づけは、切ないまでに甘く脳を痺れさせた。
閉ざされた左眼の目じりから、もう一度涙が伝い落ちる。
それはきっと、いままで流し続けてきた哀しみの涙ではなく。
幸福に包まれた、優しい涙に違いない。
高耶の手から、するりと篠笛がこぼれ落ちた。
カラカラと音を立てて転がった『伯牙』と名づけられた笛は、二人のことをまるで見守るかのように、その艶めいた身体にやわらかな日を浴びて、鈍い光を反射させていたのだった。