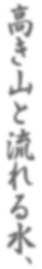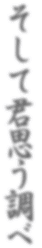To Be Continued......
書いているうちにこの話の直江が、連城響生のように思えて仕方なくなってきました(笑)。先日新刊が発売したばかりとあって、頭の中は神紋カラー一色です。書き始めた当初はまったく意識してなかったのですが、芸術系の話なので無理からぬことかもしれません。特に出逢いの場面でやたらと図々しい態度を見せるあたりが似ています(笑)。いっそのこと直江の職業を作曲家にすれば良かったかも。そして高耶さんの笛に出逢い、彼は苦悩の果てに思うのです。「あなたの笛の音で俺の曲を天まであげてくれ……!」と。しかし高耶さんが信奉するのは、直江がこの世で最も憎みながら、最も愛する天才作曲家・上杉景虎で……。
収拾がつかなくなってきました(爆)。ある意味某電柱殿下も近いかもしれません。サリエリも入っています。念のためこのお話はそんなドロドロした愛憎劇ではありません。こう、二昔前の邦画のような爽やかで切ない悲恋物語です。高耶さんも、あまりガラが悪くなくてわりと素直でどちらかと言えばケイ君に近いですが、終盤に差し掛かると共に「ああ、高耶さんだぁ」という感じになると思います。
今回で初稽古編は終えるつもりだったのですが、長くなってしまったのでぶつ切りました。まだまだ序盤も序盤って感じなので、早く話の中核となる悲恋物の展開へと進んでいきたいですね~。
……それにしても直江の家がどれぐらい金持ちなのかが気になる。何か悪いことでもしてるんでしょうか。でも車は持っていないようです。もしくは持っているけど当主しか乗れないのか。T型フォード乗り回してる直江とかも面白いけど……(笑)。ちなみにT型フォードとは、こんなの。→リンク
対する高耶さんはやはり人力車の方が似合いそう。車夫に「坊ちゃん、今日はどちらまで?」とか聞かれるんですね。何をするにつけても絵になる人だ。
第三話
指折りに数えた四日後に、日曜日はやってきた。
長い長い数奇屋塀に囲まれた、年月を経て古びてはいるが時代の味わいを感じさせる昔ながらの木造邸が、直江の住む家だった。
塀の上には夏の緑深い木々の葉と、泰山木の花。そして真っ白いなまこ壁の土蔵が覗いている。
直江は土蔵の漆喰彫刻を見るともなしに眺めながら、さんさんと光る太陽の日差しを避けて、数奇屋門の前に伸びる影の下に立って待っていた。
じりじりと、少し早い蝉の声が鳴り響き、炎天下にさらされた体は綿シャツの下で、じわりと汗が噴き出していた。
隣の家では初老の婦人が、玄関の前に立って柄杓で打ち水をしている。
目が合ったので、直江は少し会釈をした。婦人は目を細めてにこにこと笑いながらお辞儀を返す。
そんな風にして五分ほど過ぎた頃、道の向こうから、ゆらりと黒い人影が現れた。逃げ水だろうか、太陽の熱気と舗装路の冷気の間でゆらめく人影を、しばらく眺めていると、やがてその影ははっきりとした実像を結んでいく。
近づいてくるのは、利休鼠色と海松藍色に染めた麻で、縞に織り上げた着物を着流しに纏った高耶である。
左手には大きな風呂敷包みをさげ、暑いのだろう、右手は太陽の光から黒髪を守るように、白い手ぬぐいを頭の上に押し付けている。
パタパタと草履を鳴らしながら歩む高耶は、直江の姿を認めると途端にパッと手ぬぐいを降ろし、遠くから会釈をして、小走りに駆け寄ってきた。
「こんにちは、高耶さん」
「こんにちは。ごめん、待たせたか?」
「いいえ、待ってませんよ。暑いところをわざわざありがとうございました」
「本当、今日はやけに暑いよなぁ……まだ六月なのに」
額に浮かぶ汗を拭う高耶。少し日に焼けた顔が目に眩しくて、直江は心持ち目を細めた。
「やはりお迎えに伺えば良かったですね。人力か、タクシーでも呼んで」
「冗談、こんな近いのに何十銭も払えないって。別に気にしないでいいから」
おかしそうに笑った高耶はそう言い終えた瞬間、ふと、何かポカンとしたふうに直江の顔を凝視した。
「どうかしました?」
不思議に思って尋ねると、彼は「いや、その」と、言いにくそうに言葉を濁した後、
「直江さんの顔見るの、明るい場所では初めてだったから。……少し、驚いて」
「ああ。私もあなたを明るいところで見るのは初めてですね。お互い改めて〝はじめまして〟でしょうか」
おどけたように言う直江に、高耶もくすりと笑って、「初めまして。これからよろしくお願いします」と、丁寧に頭をさげた。
こうして見ると、高耶は普通の少年だった。日に焼けた肌に、黒い髪。奥二重の瞳が印象的な顔立ちは、直江とは違って良い意味で日本人らしくて、和装がよく似合う。
人目を引く容姿ではあるが、しかし初めて目にしたときのような神秘性はない。
あれは単なる目の錯覚だったのだろうか。そうだとしても、高耶の吹く笛をこれからいよいよ聴くことができるのかと思うと、やはり素直に嬉しくて、直江は心が踊るのだった。
「立ち話もなんですし、中に入ってください。冷たいものをお出ししますね」
そう言って、高耶を正門から迎え入れた。門を開ければ、緑深い日本庭園が現れる。
それほど広くはないがよく手入れされた庭には、終わり近い花菖蒲や、蛍袋。小紫や、百合、梔子、桔梗、南天、萩、そして沙羅双樹などの様々な花が、歩き進めば進むほどにそこここに咲いている。
特殊な環境ゆえに、お屋敷の類には慣れている高耶であったが、高級料亭か旅館かと見まごうようなその庭の様子には、さすがに驚いたようだった。
「なんというか、凄いお屋敷だなぁ」
母屋には寄らず、直接離れへと案内する途中に呟かれた言葉に、直江は苦笑して言った。
「ええ、私も最初見た時は驚きましたよ」
「最初?」
返されて、言葉が足りなかったと知り、
「ああ。私は養子なんですよ。幼い頃から出入りはしてたんですが」
「……そうなのか」
「もともとは〝橘〟家の三男だったんですが、直江の家に嫁いだ叔母夫婦に子供ができなくて。私が二十歳の時に、この家に入ったというわけです」
そんな話をしているうちに、二人は離れへと辿り着いた。
一言に離れ座敷とは言っても、高耶の暮らす離れとは大違いである。これだけでもう立派な一軒屋だ。
扉を開けて、中へと促された高耶であったが、そこで惑うような口ぶりでこう言った。
「あの……、お家の方にご挨拶しなくても?」
「あぁ、今日は両親とも出かけているので構いませんよ。楽にしてくださって」
直江家の当主と会うのは、さすがに緊張を強いられることだったのだろう。高耶は明らかにホッとしたように、肩を落とした。
促されて中に入ると、直江は出迎えた女中に茶の用意を頼んで、高耶を奥の見るからに上等な客間へと通した。
畳敷きの典型的純和室である。開け放たれた障子の向こうは自然を切りとったような庭園に、母屋座敷が見える。
襖絵と言い、壁の軸と言い、金糸梅の活けられた花瓶と言い、見るからに古く、そして高価そうなものばかりで、勧められるまま座布団に座ってもなんとなく落ち着かない。
ただ、おかしな話だがほとんど初対面と言ってもいいこの男の親しげな微笑のみが、高耶の心をゆるやかになごませたのだった。
「何か、手土産用意してくるべきだったな……」
失敗した……と少し俯く高耶に、直江が首を振る。
「そんなこと気にしないでください。お給金も無しに来ていただいているのに、このうえ土産まで渡されてはこちらが困りますから。そういう堅苦しいことが嫌だからあなたにお頼みしたんですよ?」
優しく笑う直江の横から、女中が現れ、盆に載せた冷茶と、茶菓子を高耶の前に置いた。
遠慮なく椀を持って茶を飲み干すと、炎天下を歩いて気づかぬうちに喉が渇いていたのだろう。カラカラの喉に冷たい液体が心地よく流れていった。
遠くの方から、チリーンとひとつ、風鈴の涼しげな音が響いた。
風通しの良い部屋は開け放たれた障子から冷風が舞い込んで、全身に纏いつくようなけだるい熱気が引いていくように感じた。
「それじゃあ……早速、お稽古始めようか」
しばらくそうして涼んだ後、高耶は持参した風呂敷包みから笛と楽譜を取り出し、向かいに座る直江に向き直る。
いよいよ稽古の始まりだ。けれど「そのまえに……」と直江はひとつ前置くように提案した。
「そのまえに、あなたの笛を聴かせてくださいませんか。私はまずそれを楽しみに今日を待っていたんですから」
いかにもわくわくした風に頼む直江。その様子に、高耶が小さく噴き出すように笑った。
「そんなに期待されても困るけど……本当に好きなんだな」
吹き手としては、好ましく感じたのだろう。彼は「いいよ」と一つ頷くと、少し気を良くしたように軽やかな手つきで風呂敷の中から、桜木をくりぬいた笛筒を取り出し、そこから白竹色の短めの篠笛を取り出した。
それを白い手拭いで拭きながら、直江に尋ねる。
「何か、曲の注文は?」
そう聞かれても、直江は篠笛の曲にどのようなものがあるのか、具体的にはよく知らなかった。
「なんでもいいです。あなたの好きな曲を」
「なんでもいい、か……それじゃあ、いまここで即興を」
そう言うと、居住まいを正し静かな所作で笛を構えた。
即興に調音はいらない。彼は唄口に唇を乗せて、息を吸い込んだ。
その瞬間、高耶のまとう空気が一変したのを直江は感じた。
歌口に息を吹き込む。ピーッと、甲高い音がそこから響いた。
蝉の声が、とたん静まり返ったようだった。
続けて先程よりも高い音を。空気を突き破るようにして、奏でる。
(これは……)
笛の音以外、何の音も聞こえない。
いや、そうではなく、すべての音が、高耶の笛と調和し、溶け込み、調べの一部として笛の音を包んでいるのだ。
サヤサヤと、葉を揺らす風の音を、笛の調べから感じる。
美しい音が、鼓膜の底に鳴り響く。
目を閉じ、奏でる高耶の姿は、やはりあの日見たときと同じように美しく、神秘的な空気に包まれ、目の錯覚などではなかったのだと、改めて思い知る。
ひとつひとつ、ゆったりと流れるように生まれ出でる調べ。
本物だ、と直江は感じた。
十年近くの間、あの家の前を通るたびに聞き入っていたその笛の音。
しかしその、押し殺すように抑えられたかすかな音色ではなく、いま目の前に展開する、高耶自身が本来持つあるがままの演奏を初めてこの耳で聴いて、改めて思い知った。
時が止まったように、笛の調べに聞き入っていた。
流れるように移り変わる音の数々を、ひとつも逃さぬように。
風のような笛の調べが、やがて最後の音を鳴り終えたことさえ気づかないほど、直江は高耶の笛の音に魅入られていた。
「直江……さん?」
しばらくして、曲が終わっても呆けたように、何の反応も返さない直江に、高耶が少し不安そうに呼びかけた。
ハッとして、やっと意識を戻すと、正面には笛の演奏を終えた、普段どおりの高耶がいた。
「期待はずれだっただろ?」
反応の鈍さに、「やっぱり駄目か」と、がっかりした風に言う彼に、直江は「とんでもないっ」と、ブンブン首を激しく横に振った。
「期待はずれだなんて、とんでもないです。素晴らしかった。予想以上でした。やはり、遠くから聞こえる笛の音も良かったですが、こうして近くで、吹き手の姿を見ながら聴くのとでは、全然違います」
興奮しながら語る直江は、感極まるあまり、両目に少し涙が滲んでいた。その様子に高耶はびっくりしたように目を瞬かせ、
「大袈裟だな」
と素直じゃない返事をしながらも、やはり褒められて嬉しかったのだろう。口元をまげながら、頬を赤く染めているのが印象的だった。
「でも、オレなんて本当に、まだまだだよ」
「そんなこと。絶対、才能あると思いますよ」
未だに胸の動悸が止まらない。
実際、これほどまでに心惹かれる音楽を聴いたのは、直江自身初めてだった。
友人と劇場にオペラやオーケストラのコンサートを聴きに行った時も、その壮大華麗さに聴き入りはしたものの、ここまでの感動は覚えなかったのである。
それは吹き手本人の人となりなどは抜きにして、純粋な音楽的評価として、そう思うのだ。
しかし高耶は、それを単なるお世辞だと思ったのか、
「そんなことない。直江さんはちゃんとした笛を聴いたことないからそう思うんだ。前にも言ったけど、氏照兄の笛はもっと凄いし、家元は言うまでもないけど、氏政さんや、他のお弟子さんに比べたらもう……」
はぁ、と大きくため息をついて、彼はしょぼくれたように肩を落とす。
そういうものだろうかと、直江は首を傾げた。確かに、高耶の笛はまだまだ荒削りなところがあったが、彼の言う「氏照兄」や、「家元」や「他の弟子達」の調べを聴いて、ここまでの感動を得られるとは思えない。
もちろん専門的な評価を下せるほど笛に詳しいわけではなかったが、高耶の笛には、技術的なものとかそういったのとは違う、もっと別の次元の何かがあると思った。
「今のは独奏だから、まだいいんだ。即興で好きなように吹いただけだし。これが合奏になると本当にダメで。午前中の稽古でも奥様の三味線と合わせたんだけど、もう、ボロクソに怒られた」
どうも、独りで自由に吹くのは得意だが、人と合わせたり型にはめられたりするのが極端に苦手な性分らしい。
しかし直江は、確かに彼の笛の音の奥に、密やかながらも稲妻光るように鮮やかな天賦の才を感じ取ったのである。それは決して技術や経験だけでは身につかない、選ばれた者だけに神から与えられたものだ。
このうえ彼が、修行を重ねることによって熟練した技術を自らのものにすることができたなら、いったい如何ほどの芸術がそこから生まれるのだろうと、直江は身震いする思いだった。
「まぁ、いいや。さて……それじゃあそろそろ笛のお稽古の方、始めよう」
「え、あ、はい。よろしくお願いします」
興奮冷めやまぬ胸の鼓動を抑えるように直江が言うと、高耶は風呂敷の中から笛の包みを取り出し、それを開けるとズラリと10本ほどの大小さまざまな篠笛が現れる。
「たくさんあるんですね」
物珍しそうに覗き込む直江に、高耶はそのうち中くらいの長さの、竹の素の色の笛を取り出すと、差し出した。
「篠笛は歌舞伎や長唄、祭囃子と用途がさまざまで、その場合に応じて一笨調子から十二笨調子ぐらいまで、使い分けなければならないんだ」
直江は両手に受け取った笛を見ながら、感心するように頷いている。
「その笛は七笨調子七孔の唄用で、篠竹製天地籐巻き。頭の部分に〝七〟って数字が書いてあるだろう?初心者の人は七か八あたりから入るのが一般的なんだ。しばらくの間は七笨だけで練習するつもりだから、その笛は直江さんにやるよ」
「えっ?そんなの、いただけませんよ」
慌てて笛を戻そうとする直江の手を、高耶が苦笑しながら押し返す。
「別に遠慮するなって。七笨のは他にもいくつも持ってるから」
「でも、お高いものなんでしょう?」
「まさか。そんなの自分で作ったやつだし」
えぇっ!と直江が大袈裟なぐらい驚きの声を上げた。
「自分で作れるんですか?」
「ああ、オレの持ってるやつはほとんど手作りだよ。兄さんからもらったのも何本かあるけど」
高耶はなんでもないことのように言うと、包みの中から直江にあげたものと同じ長さの笛を取り出した。ただしこちらは黒光る柿渋色である。
「すごい。器用なんですね……」
「そうでもない。作ってるとき何度も指切っちまったし。けど想像するほど難しくないから、もう少し経ったら自分で作ってみるといい。さすがに専門家の先生の作ったものとは音が違うけど、自作だと愛着わくから」
そのうち道具一式貸してあげるから、と語る彼だったが、そんなものを本当に自分で上手く作れるものなのだろうかと、直江は少し不安になった。
そんな会話を交わしつつ、直江の初稽古が始まったのだった。